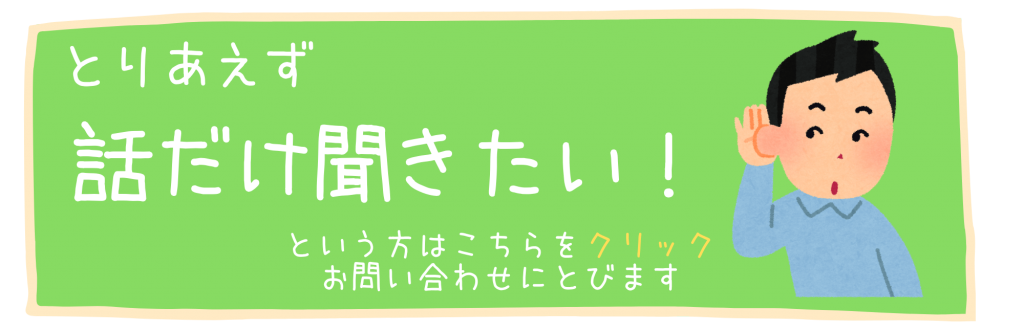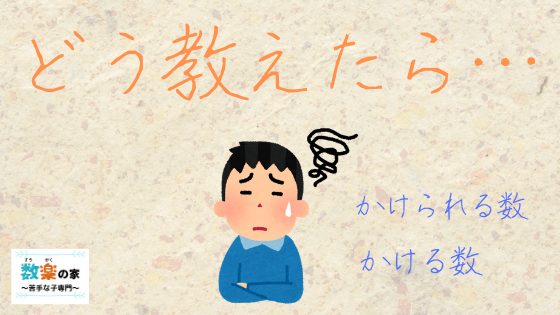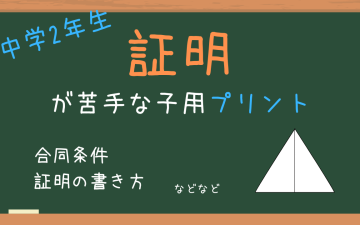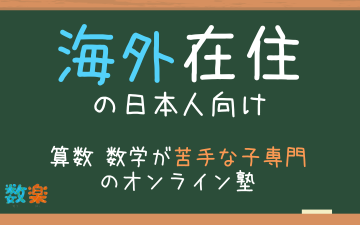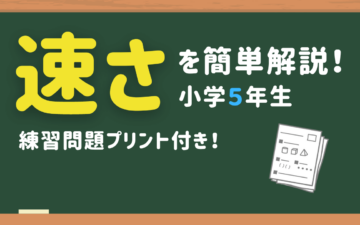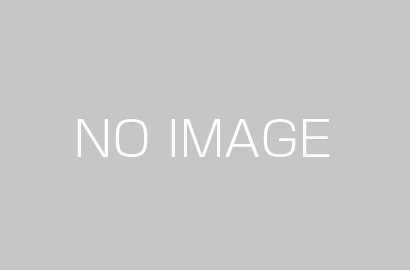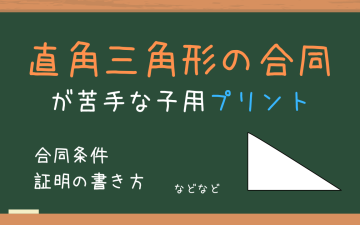「かける数とかけられる数はどっち?」と聞かれたらすぐ答えられますか?小学校で習うかける数とかけられる数、文章を読んでどっちがどっちに来るのか順番(順序)が曖昧になったり、式が逆な時に「なんでこうなるの?」という疑問にすぐ答えられるのか心配になると思います。親としてしっかり説明してあげなくては!と意気込むと思わぬ落とし穴になるかもしれませんので今回は算数が苦手な子にたいするアプローチもお伝えします。
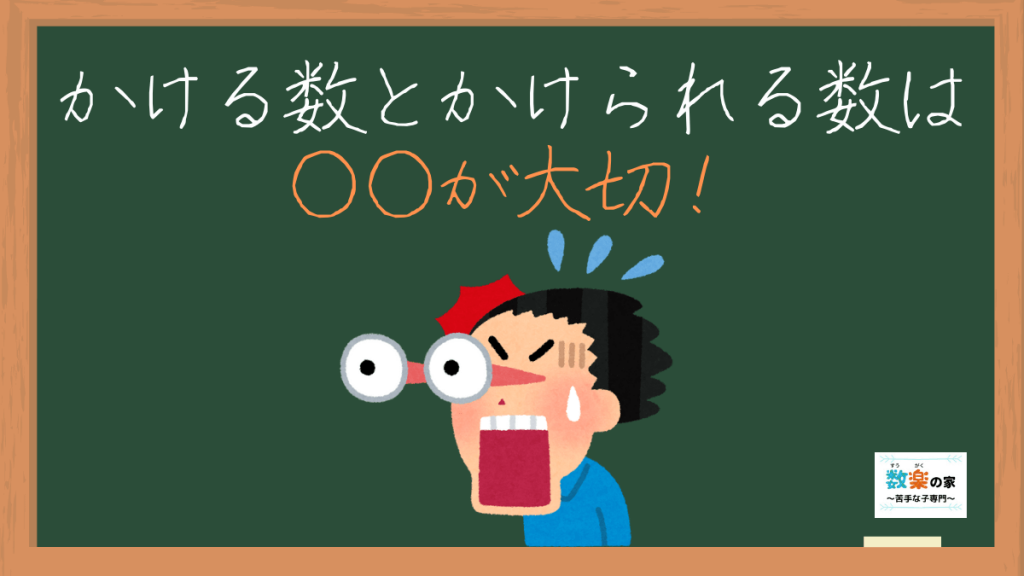
かける数 かけられる数とは
先にある数が「かけられる数」で、 後にある数が「かける数」になります。これをふまえて考えてみましょう。
「何を聞かれているか」が大事
かける数かけられる数(かけ算のきまり)を解くときのポイントは何を聞かれているかです。
例えば
【リンゴが5個ずつ4枚のお皿に盛ってあります。リンゴは何個あるでしょう。】
という問題があるとします。
この問題で聞かれていることは「リンゴは何個あるでしょう」。つまり「何個」です。聞かれていることが何個だったら最初に持ってくる数字は「個数」になるので
「リンゴ5個」×「お皿4枚」=「20個」となります。
同じ単位で挟んであげる、この方法はサンドイッチ法と言われています。ここで気を付けないといけないことは、教えようと一生懸命になりすぎないことです。(※無理強いさせてしまうと拒否反応が出てしまいますのである程度教えて分からなければそのままサラッと流してあげましょう。)
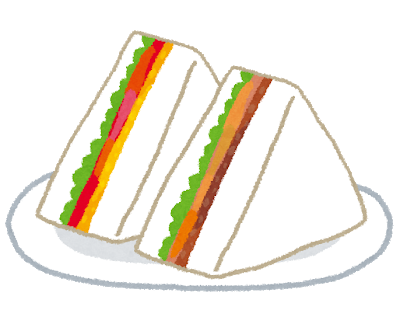
例題
□アメをひとり3個ずつ配ります。7人に配るためにはアメは全部で何個必要ですか?
聞かれているのは「何個」
ということは最初に持ってくるのは個数の3。
3個×7人=21個
□折り紙をひとり5枚ずつ配ります。6人に配るためには全部で何枚必要ですか?
聞かれているのは「何枚」
ということは最初に持ってくるのは枚数の5。
5枚×6人=30枚
【PR】
質問してあげる
文章問題は文章を読んで結局何を聞かれているのかが分からないと問題は解けません。
小学生は文章を適当に読んだり、数字だけを見て式を立てようとしがちです。
何を聞かれているか理解できてないと、ゴールが見えてないのに走っているのと同じになります。
子供に「分かった?」と聞いても反射で「分かった!」と言ってしまうので「これは何を聞かれてる?」と確認を兼ねて質問してあげましょう。
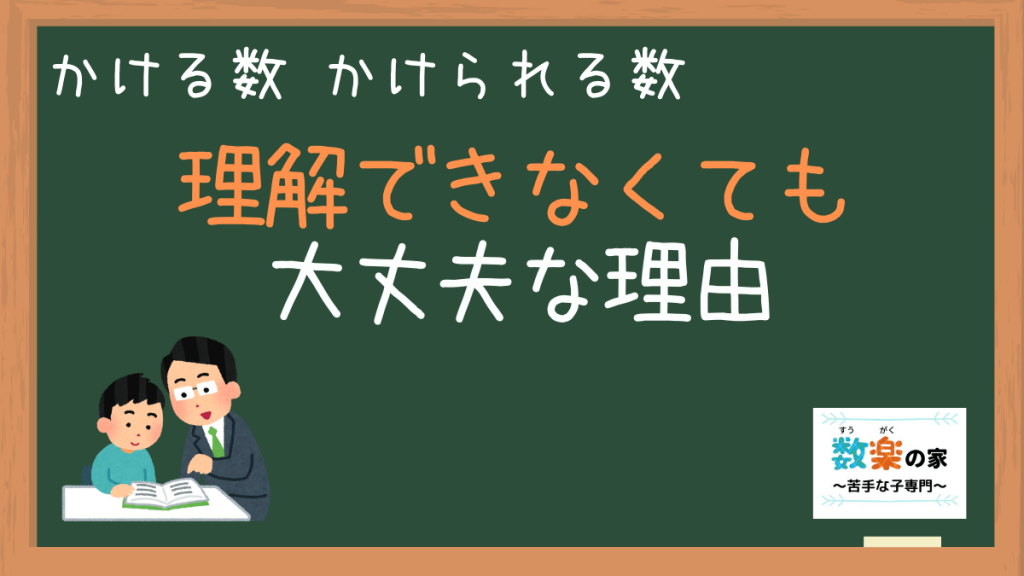
「かける数」と「かけられる数」は無理して覚える必要はない!
説明してもどっちがかける数でどっちがかけられる数になるか理解できない時は理解できなくてもOKです。
その理由は、
かけ算を習い始めの2年生、3年生はまだかけ算をするだけで精一杯です。そんな時に、「何個のいくつ分か」などの概念的なことを理解しなさいといっても逆に混乱して分からなくなるだけです。
混乱する→分からなくなる→算数嫌いになる
のパターンになってしまってはもったいない……。概念的なことは、成長していけば自然と分かるようになります。それよりも大事なのは「だされた問題が何算なのかを理解できているかどうか」です
学校のテストではピンになる
残念ながら学校のテストでは「かける数」と「かけられる数」を逆にかくとピンになりますが気にしないでください、学校は指導要領通りに教えないといけないというのがあるのでピンにしないといけませんが、
かけ算の答えがあってれば大丈夫です。
かける数かけられる数は掛け算の文章問題です。とりあえず文章を読んでかけ算の式を作って答えが合っていれば、「掛け算はしっかりできている」ということなのでどっちがどっちかは一旦横に置いておきましょう。
子どもの一番の原動力は「楽しい」という思いです。ゲームが好きな子はずっとゲームするし、工作が好きな子はずっと工作をしますよね。それと一緒で算数も楽しければ自然と勉強します。どうしても分からせたいなら無理に詰め込もうとせずに楽しく学べるような工夫をしてみましょう。
苦手な子にたいする誉め言葉
もし学校のテストで「かける数」と「かけられる数」が逆でピンになっていたとしても掛け算が書けていれば褒めてあげましょう。
「ピンになってるけどこの問題が掛け算なのはわかってるから凄いね!」と一言褒めてあげるだけで子どもはポジティブな心になれます。親からすると小学校の時期に理解できてないのは危ないのではないか...と考えてしまうかもしれませんが子どもは成長するにつれて理解できるようになるので心配ありません。
褒め方や声のかけ方で勉強に対するモチベーションは変わります。保護者様向けの「算数の教え方のコツ」もお伝えしていますのでぜひご利用ください。
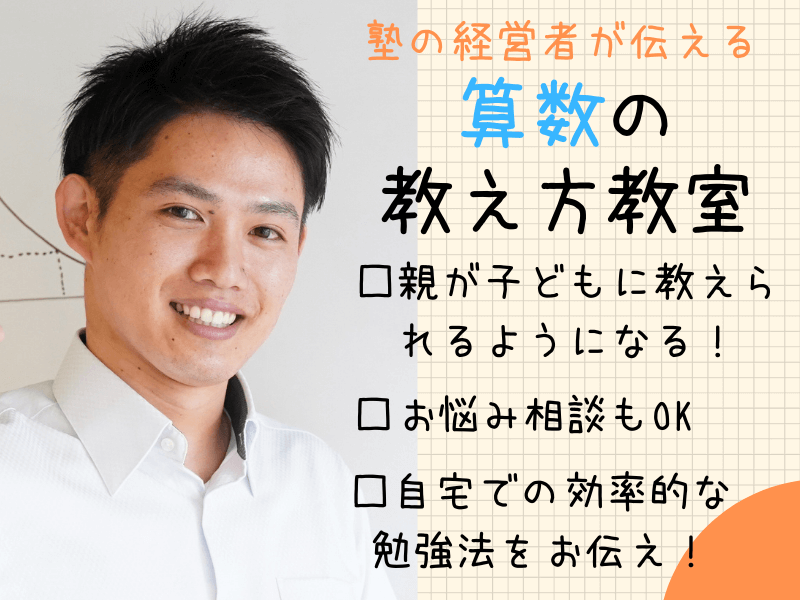
時間があれば
「かける数」と「かけられる数」に目が行くということは教育に対しての意識が高いということです。もし時間に余裕があるなら子どもの数字とノートの書き方も見てあげてください。
数字は丁寧に書く練習をしておかないと見間違いにつながります。よく見るのが1と7、4と9、0と6です。「せっかく問題の解き方は分かってたのに!」とならないように早めから丁寧に書く癖をつけておいて下さい。ノートの書き方も同じ理由で数字を小さく書いていたり途中式を省いているとミスにつながります。特に分数の時は、ノートのマス目を気にして小さく書きがちです。小さく書けば見間違いにつながりますのでこれも注意をした方が将来に役立ちます。
まとめ
かける数とかけられる数、掛け算なんだからどっちがどっちでも変わらないはず……。という考えで大丈夫です。この単元は小学2年生で習いますが、低学年には理解しにくいので、とりあえず「この問題は掛け算!」というのが分かっていればOKです。無理して説明すると混乱して算数嫌いになってしまうこともあります。小学生のうちは勉強って楽しい!と思えるような教え方をしてあげましょう。
数楽の家
数楽の家は不登校に対応できる塾でもあるので、学校に通っておらず勉強が止まっている生徒も気軽に通うことができます。ホームスクーリングの教え方や保護者様向けの「算数の教え方のコツ」をお伝えするコースもあり、算数数学のリカレント教育、大人の算数やり直し塾、も行っております。
小学生は算数教室、中学生は数学の個別指導、県外の方には算数数学のオンライン授業 (早朝オンライン)も行っています。また、教材として算数プリントも無料でダウンロードできるようにしているのでテスト前の復習などにお使いいただけます。 ホームスクーリング用の算数プリントもありますので家庭学習での宿題などにもどうぞ。